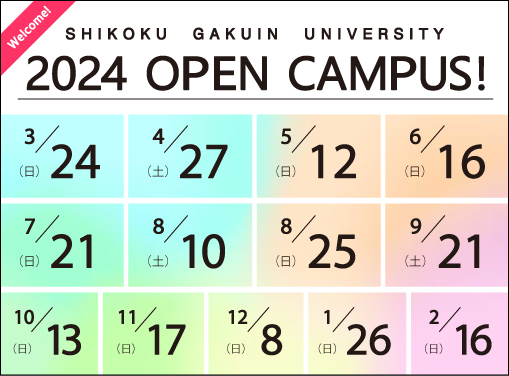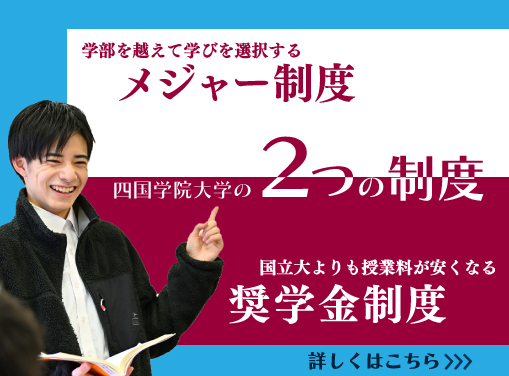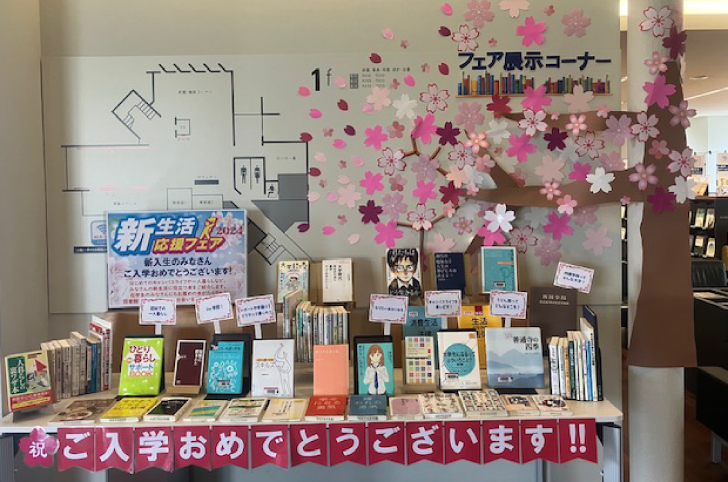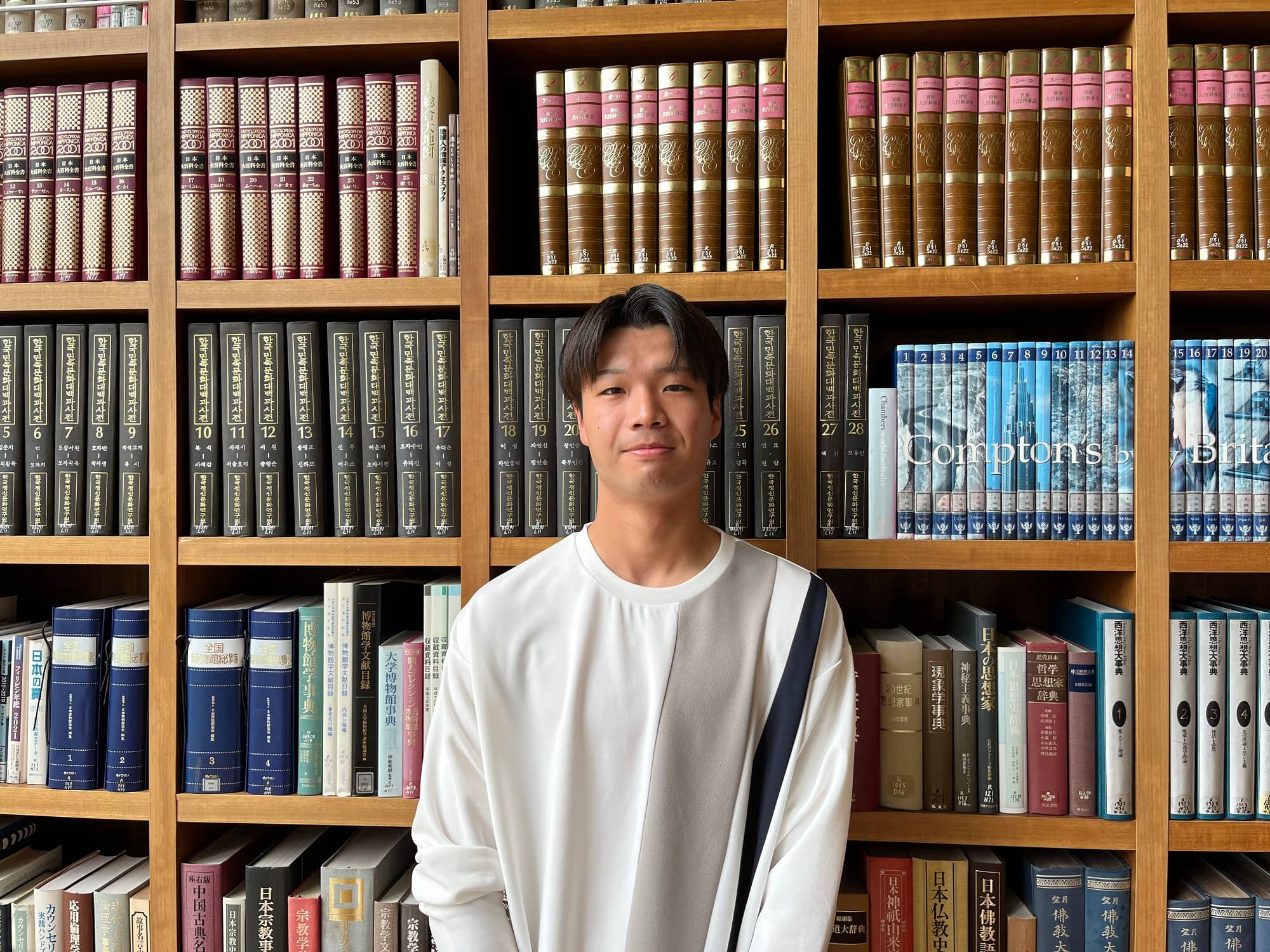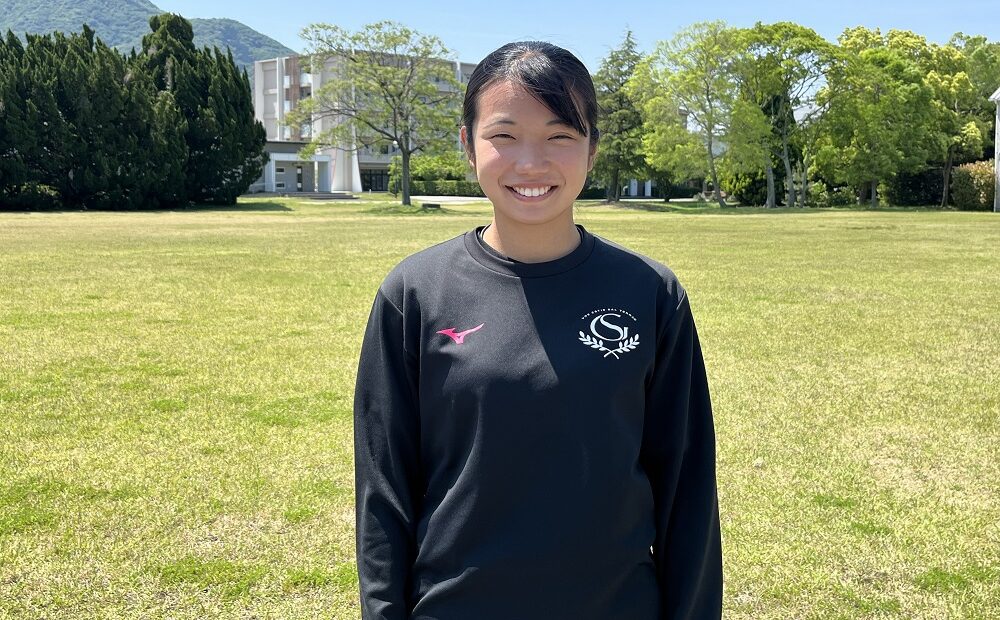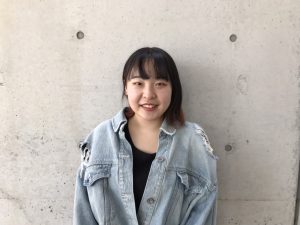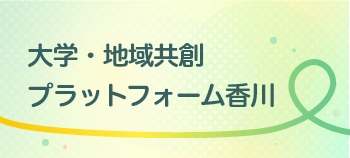人間を問い、知を生きる
PICK UP
FEATURES
メジャー制度
自由さが魅力のメジャー制度。
1つのメジャーを深めることも、学部を超えて複数のメジャーを組み合わせることもできます。
アスリートとしての
新たな価値を見出したい

経営と様々な分野を
結びつけて学びたい

演劇を活かせる
保育士になりたい
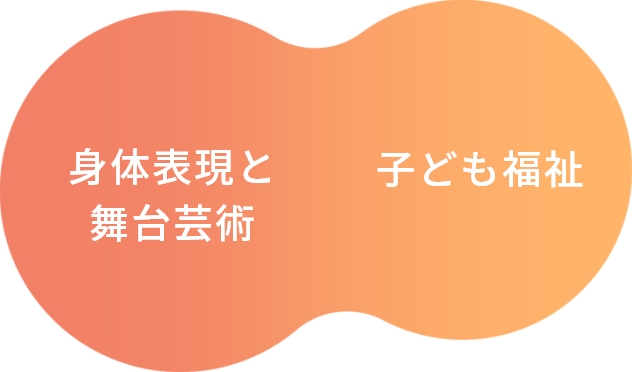
文学部社会福祉学部社会学部
TOPICS
すべて▼
- すべて
- News
- イベント
- 学生活動
- スポーツ
- プレスリリース