観光学メジャー

メジャーの学びのポイント
観光をテーマに「自身の興味関心」を探る
観光学は学際的に幅の広い学問です。「観光学概論」や「観光対象論」では、観光学がどのような学問であるのか、またどのようなモノを観光対象と捉えるのかの理解を深め、自分自身が興味関心のあるテーマを見つけます。
実践的な学びと座学での実学で実力をつける
「観光学実習」や「観光情報技術論」では「観光」をテーマにした研究や制作のための授業を行います。また、「旅行業務論」では国内外の旅行業の実態について学びます。観光学では理論や概念といった知識だけでなく、実践型のスキルアップを目指します。
持続可能な社会での観光のあり方を考える
これまで観光学では、「地域振興」や「娯楽産業としての商品提供」を検討できる人材育成が企図されてきました。SDGsの取り組みが世界的に急務となった昨今、社会的課題を検討できる人材を育成します。
PICKUP授業
『観光学概論』
今日の私たちの日常生活に溶け込む『観光」を捉え直し、その意味や歴史、効果や対象、産業やマーケティングと経済と言った、観光学が織りなす学際的知識全般についての基礎的な考え方について学びます。
『観光学実習』
ツアー・プランニングとツアーの実施、観光資源・施設の開発調査、観光PRのための動画やリーフレットの制作、国や地方自治体の観光振興のための事業に参加するなど、現場での実践を通して観光分野の企画実践力を修得します。
『観光情報技術論』
観光資源に限らず、わたしたちが日夜目に触れる「映像コンテンツ」について、企画技術力、撮影技術力、編集抜術力を修得し、批料的に読み解く力や魅力的に発信する力の基礎を、講義・実習・演習方式を用いつつ養います。
学生の声

実践型授業で、旅行の企画力を養う。
観光地に行って情報収集し、ツアープランを組み立てたり、パンフレットを作成したりしています。実践型の授業を通じて、その土地にしかない景色、食、体験の魅力を発見するのが何より楽しいです。
学びを生かし、将来は地元である香川県の発展に関わりたいです。
.jpg)

興味のあることをとことん探究。
家族旅行の楽しい思い出がきっかけで、観光学メジャーを選択。旅行プランを作る授業で効率よく旅する方法を学び、その後の韓国旅行で役立ちました。マイナーでは海外の文化も勉強。もっと外国のことを知りたいし、訪れたいです。
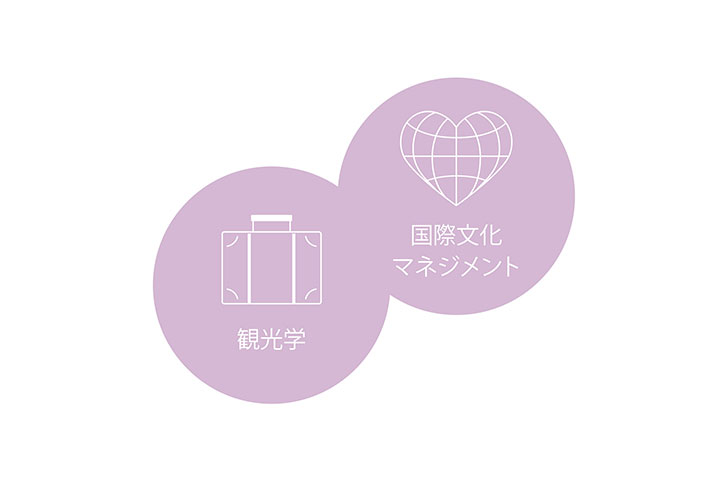
組み合わせて学ぶ
