社会福祉学メジャー

メジャーの学びのポイント
社会福祉における対話の重要性について考える
自分とは違う考え方の人とコミュニケーションを取ることは簡単ではありません。ソーシャルワーク演習、社会福祉学演習などの科目で他者と関わる体験を通じて、対話の意味とその難しさを考えます。
社会福祉の本質について考える
社会福祉とはそもそも何なのか。社会福祉に関するさまざまな学びの根底となる問いを、社会福祉概論、社会福祉の歴史、社会福祉の原理と政策などの科目を通じて考え、社会福祉の本質を探求します。
多様性を尊重する社会のあり方を考える
多様性を大切にするためには、関心を持ち、正しく理解し、違いを受け容れ、認め合う寛容さが必要です。国際社会福祉論、多文化共生福祉論などの科目を通じて、多様性を尊重する社会のあり方を考えます。
PICKUP授業
『社会福祉法制』
社会福祉の主要な論点を取り上げて、現状と課題、政策や制度改正の動向などを概説します。法制度の基本的な理解をふまえて、これからの社会福祉のあり方を考えてください。
『国際社会福祉論』
世界のさまざまな社会問題に関する国際的な社会福祉の取組みについて、具体的な事例を紹介しながら解説します。また、北欧と日本の社会福祉を比較して、日本の福祉の進むべき方向を考えます。
『ソーシャルワークの基盤と専門職』
ソーシャルワークの専門性を発揮するには、相談援助の概念と理念、特に、その価値、知識、方策、方法からなる方法論への理解が基盤となります。本講義ではこの基盤について概説します。
学生の声
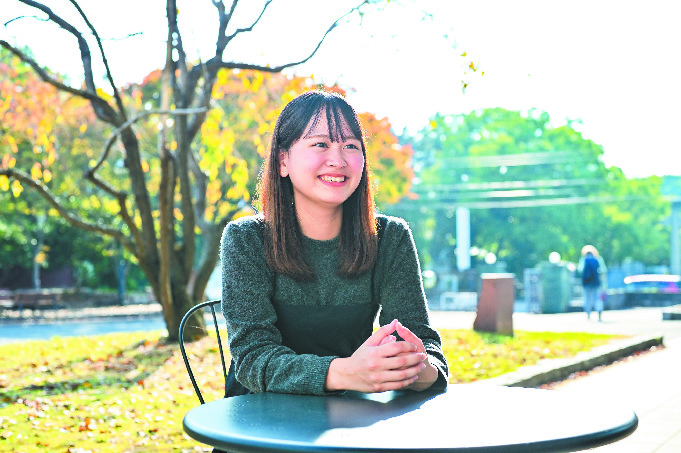
資格取得で福祉支援の幅を広げていきたい。
理念や歴史、意義などの講義と、子育て支援施設への現場実習がバランスよく組み込まれ、実践的に学べます。運動部のマネージャー経験から支える立場にやりがいを感じてきたので、「社会福祉士」の資格を取得し、さまざまな人をサポートしたいです。


夢は、児童相談所で誰かの居場所になること。
過去にお世話になったことから、ソーシャルワーカーを志すように。スクールソーシャルワークも同時に勉強し、より学びを深めています。授業は自分の先入観を払拭し、気づきを与えてくれるものばかり。今後に生かしていきたいです。

組み合わせて学ぶ
