平和学メジャー

メジャーの学びのポイント
暴力の本質に迫る
平和の対立概念は「暴力」です。最も悪質で極端な形で現れる暴力が戦争と言えます。 一方で貧困や経済格差を「見えない暴力」と捉え、暴力の構造を分析して解決の道筋を探ります。
戦争の背景を探る
戦争は最も複雑な社会現象ですが、SNS時代の戦争は単純化された物語になります。なぜ戦争が起きるか?それは「一方的な正義」で戦争という物語を語ることに起因するのではないでしょうか。
決して一つではない 「正義」について考える
国際関係は多様な価値観を理解する必要があります。自国の正義を押し付けることは、衝突の火種となりかねません。「正義の戦争」など存在せず、「人間を殺害する正義」など詭弁に過ぎないのです。
PICKUP授業
『平和学』
半世紀前、全国初の平和学講義が本学で始まりました。世界情勢と国内体制は大きな変遷を遂げる中、改めて平和学が社会に提起する課題を確認し、私たちができることを考えます。
『国際関係論』
国際関係は世界大戦後に国連など「国際ルール」を設ける一方、数多くの個人の貢献が成果を上げてきました。国際秩序について、制度と市民の両方の観点から学修します。
『マイノリティとダイバーシティ』
社会の中で少数派とされる人々(マイノリティ)について学びます。社会的マイノリティへの理解は社会の多様性(ダイパーシティ)を実現するために必要不可欠な知識です。
学生の声

多角的な視点を得て、人としても成長できる。
ある国の正義が他国から見れば悪…など、あらゆる角度から平和や幸福について光を当てていくので、視野が広がります。内容も国際紛争や公害、SDGsと多彩。平和教育の本質を知り、自分の偏見に気づくことで、世界を見る目が変わっていきます。
.jpg)
一つの分野を学ぶ

現実を知り、未来を考える奥深いメジャー
大学には興味のあるメジャーが数多くある中で、一番気になったのが「平和学」。授業で戦争の悲惨な映像で生々しい現実を知り、もっと深く学びたいと思いました。どの分野にも通じるものがあり、人としても成長できる学問です。
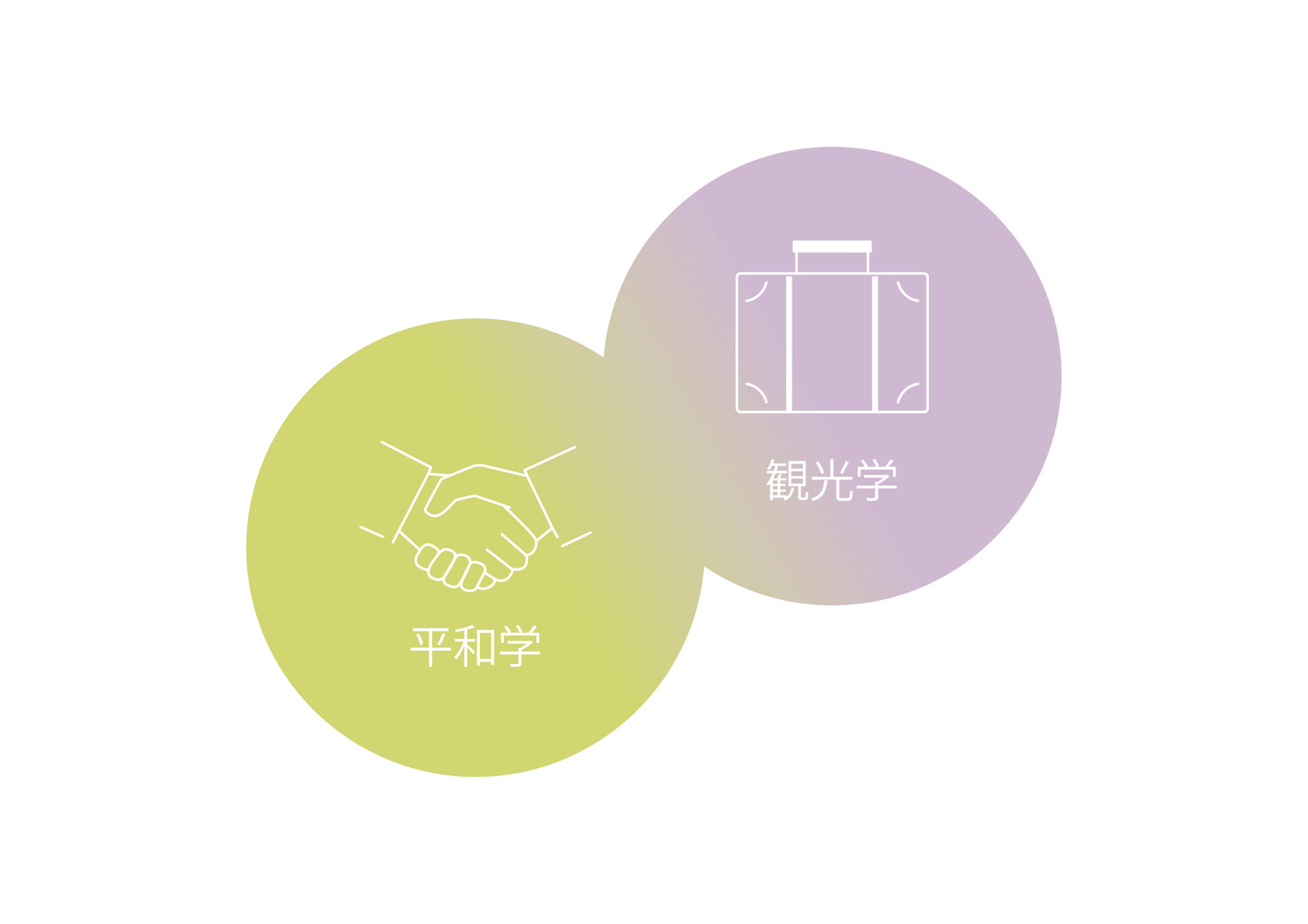
組み合わせて学ぶ
