メディア&サブカルチャー研究メジャー

メジャーの学びのポイント
メディア社会を生きる力を磨く
マス・メディア、ネット・メディアの機能や影響、メディア・コミュニケーションのメカニズムを学び、メディアの情報を読み解く力、それだけでなく発信する際に必要な能力も磨きます。
多様な文化を多角的に理解する
音楽、映画、マンガ、小説といったコンテンツ、スポーツやファッションそしてテレビやインターネットやSNSなど、大衆文化やメディア文化について分析・理解する方法を学びます。
メディア・文化の観察から人間を理解する
消費、流行、ファンダム、炎上などさまざまなメディアや文化の現象を、メディア論や社会学の視点から分析することを通して、人間とはどのような生き物なのかを学びます。
PICKUP授業
『現代文化論』
日本または世界のポップ・カルチャーについて、社会の流動性・産業・技術など多角的な視点から理解し、ディスカッションを通して他者と意見を交わす力を身につけます。
『メディア研究』
メディアをとりまくさまざまな現象について、メディア論や社会学の視点から考えます。メディアとは何か、メディアを利用する人間とは何か。知見を学び、考え抜きます。
『情報社会論』
メディアが媒介する視覚・聴覚情報の歴史と理論を学びます。人類の文明史を情報という観点から学び、現在と未来の情報について批判的な視点と想像力を養います。
学生の声

サブカルチャーを学んで得た、今までと異なる視点。
「サブカルチャー」というとゲームやアニメなどをイメージしがちですが、言葉の持つ本当の意味や歴史を学び、社会の見え方が変わりました。もう1つの専攻である経営と情報加工の学びも生かし、将来はメディア業界の就職を考えています。
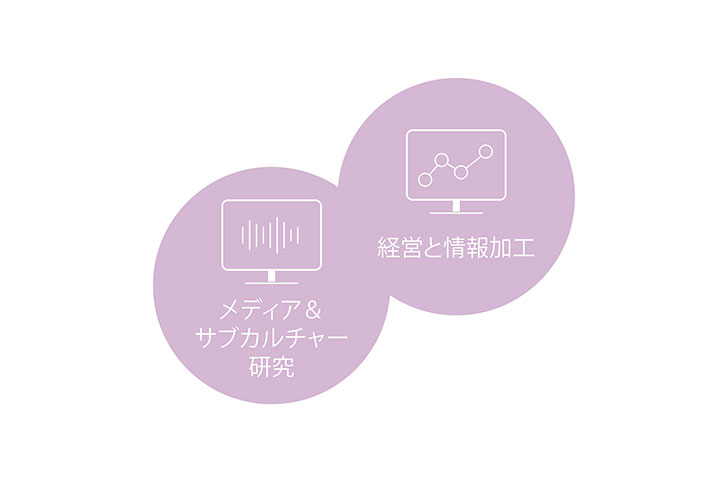
組み合わせて学ぶ
