日本語・日本文学メジャー

メジャーの学びのポイント
ことばとの出会いを大切にする
文学作品に触れると、今まで知らなかったことばや、聞いたことがあるけれどわからないことばに出会います。それらのことばのルーツを知ることによって、思考力が養われ、新たな世界が目の前に広がります。
多様な「読み」にチャレンジする
文学は、一文に様々な意味が交差している場合があります。つまり読み手にとって大事なのは解釈です。「誤読」を恐れずに、思い込みの「まちがい」を問い直し、テキストとの新たな向き合い方を習得します。
想像力を追求し、自らの感性を磨く
多様な社会的文化的背景の中で培われてきた文学作品を読み、色々な顔を持つ登場人物の立場に身を置き、その背後にある光と闇に目を向けます。共感力、洞察力を育てることで、自らの感性を磨きます。
PICKUP授業
『日本文学概論Ⅰ』
「日本文学」という学問の研究対象を明らかにし、ついで研究方法を論じます。本講では特に「心理学」の方法論を援用した文芸研究を紹介します。
『日本文学史AⅠ』
「本当に信じうるもの」をめぐる近代日本文芸の歴史を概観することで、日本の近代小説がいかなる課題を背負って始まったのかを理解します。日本の近代文学史の根本テーマを「信仰の間題」と捉え、その規点から主要な作品を講読していきます。
『文芸創作演習』
創作表現のための講義と作品作成を行います。作品の基本設定、特に語りの設定を概説し、それぞれの語りの長所と限界を理解します。プロットの作成においては、企画書としての性格を考慮して作成します。
学生の声
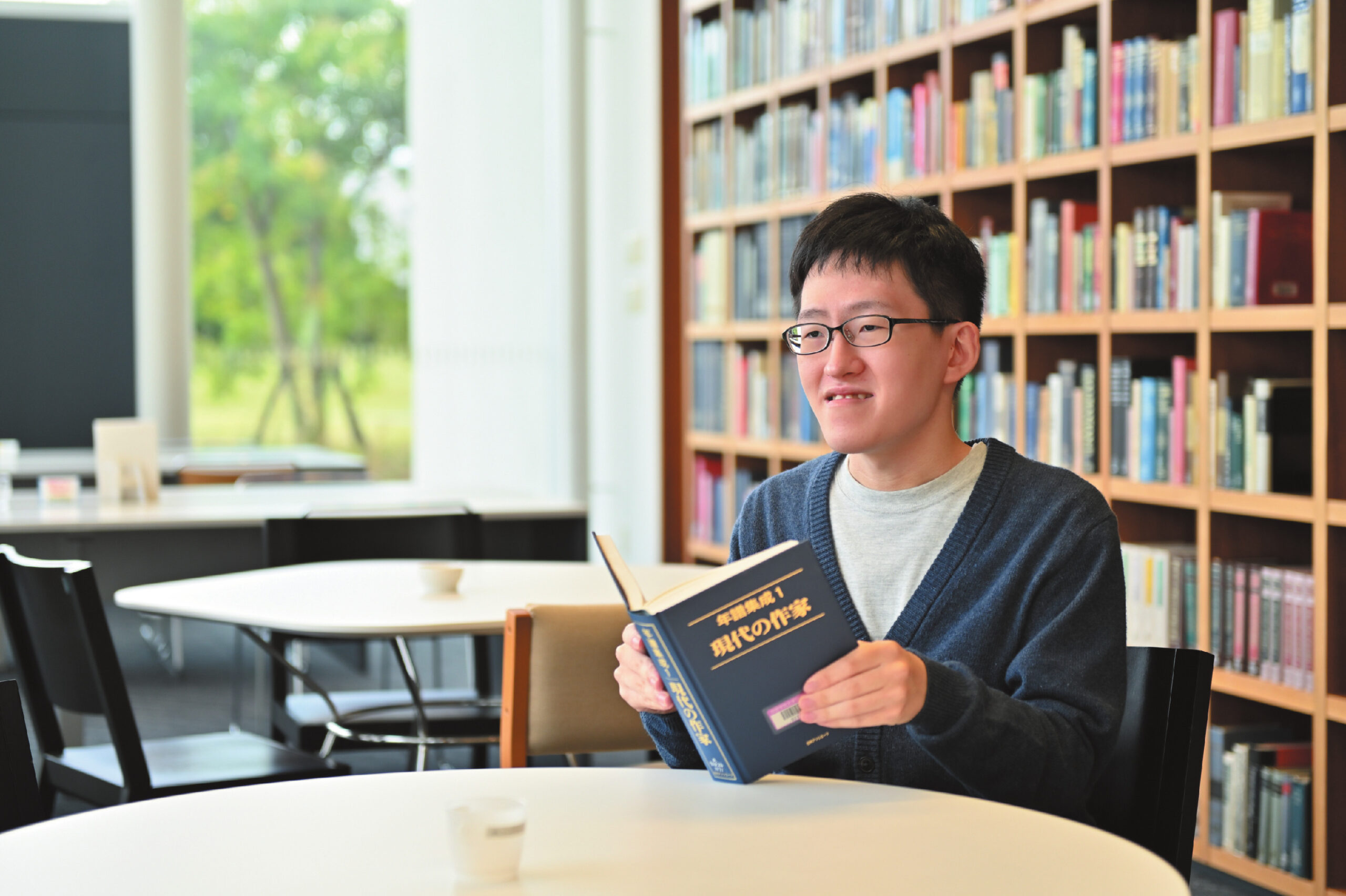
文学への理解を自然と深められる授業内容。
ここで培える“物事を深く読み解く力”は、人生のさまざまな事柄に応用が可能です。心理学的観点から小説を分析する授業が興味深く、「心理学・カウンセリング」メジャーも選択。学部を越えて好きなことを学べるので、毎日が充実しています。
-1.jpg)
組み合わせて学ぶ

作品と向き合い、より深く理解する
日本文学演習の授業は、作者の生い立ちや時代背景を理解して、小説に込められた作者の心情を読み解くのが面白いですね。英語・英米文学メジャーで海外文学も勉強しています。卒業研究では小説の執筆を経験。今後も続けたいと思います。
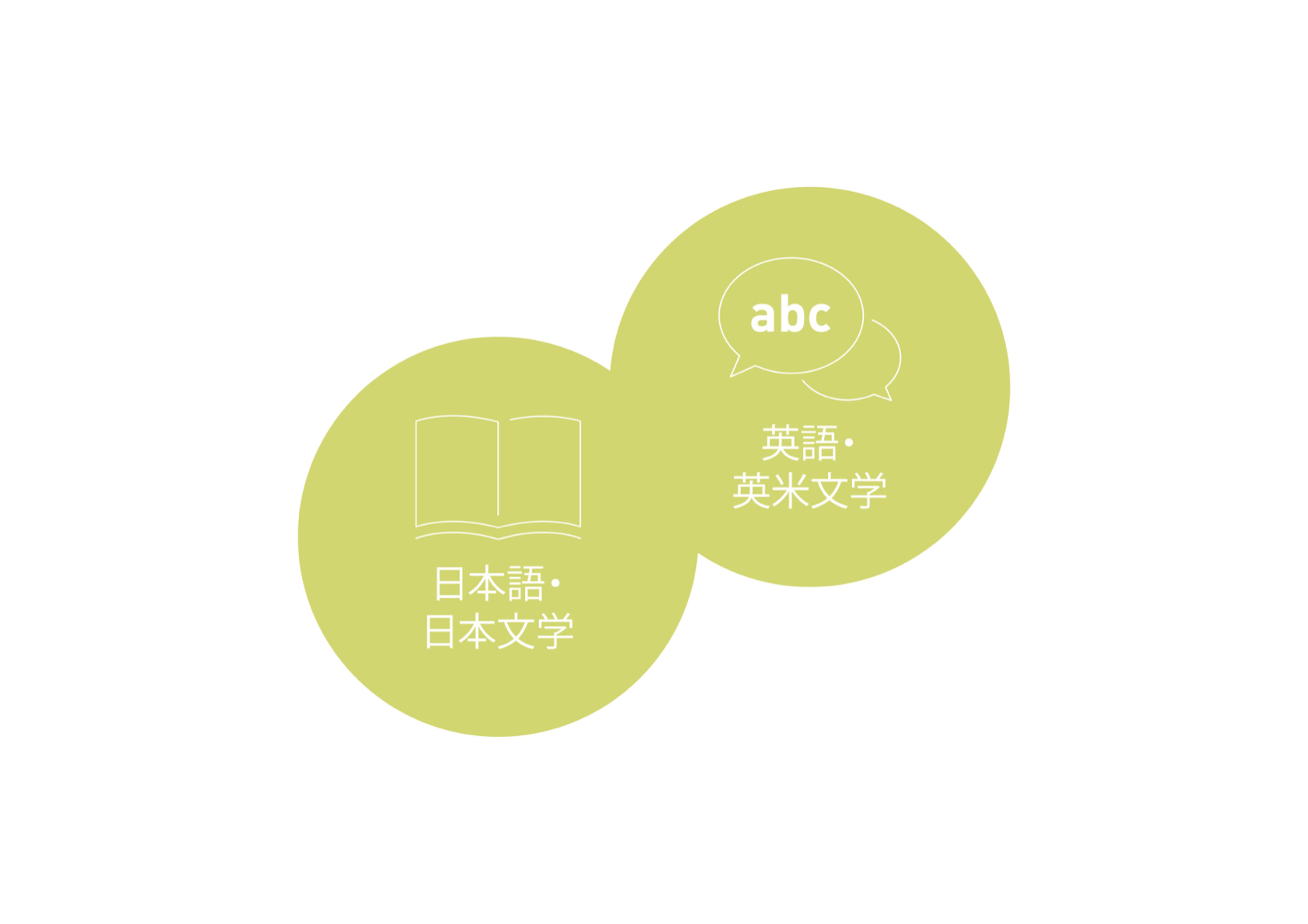
組み合わせて学ぶ
