歴史学・地理学メジャー

メジャーの学びのポイント
社会の事象を時間軸と空間軸で考察する
現代社会がどのように形成されてきたのかについて、歴史学的な時間軸と地理学的な空間軸の変化をみることで、総合的な構想力を養います。それは歴史的資料や地図を読む学習を通して行われます。
「世界のなかの日本」を構想する力を養う
一国史としてではなく、世界史の動きと関連して変化してきた日本史のあり方について学びます。人類史における戦争と平和を軸に、未来における世界のなかの日本について構想する力を養います。
「日本のなかの世界」を構想する力を養う
古代から日本列島がどのように世界と関係していたのか、その痕跡が現在どのような形で日本社会の一部として存続しているのかを学び、歴史学・地理学における普遍性と特殊性について考える力を養います。
PICKUP授業
『日本史通史Ⅰ』
高校日本史の内容について通史的に、もう一度、受験日本史ではなく、地域史にも目を向けながら最新の研究の内容をも織り込んで講義します。講義を通じて、より豊かな歴史像形成を目指します。
『近現代史資料講読』
講義のテーマは、「史料の読み方を身に付ける」。目的は「自前の歴史認識を作る」。手紙、日誌、公文書など様々なレベルにおける史料を読み、その歴史的位置付けを共に考えます。
『地図・地理資料を読む』
地理学研究の基本となる地図の歴史や読み方や、地理資料の用い方、また、分析の仕方を、演習及び実習形式で学んでいきます。大学周辺を調べる巡検(フィールドワーク)も実施予定です。
学生の声

好きな分野に没頭できる環境が魅力。
最初は戦国時代に興味があったのですが、たくさんの講義を受ける中で知的好奇心が高まり、戦前・戦後の経済状況など、今は近現代史を探求。他学部の授業「ベースボール史」で知識を深めるなど、ジャンルを問わず好きなことに没入できています。
.jpg)
一つの分野を学ぶ

歴史を学ぶことで培われる考察力
古い資料やデータから、歴史をひも解いていくのがこのメジャーの醍醐味。文学も専攻していますが、物語の時代背景を理解しておくと、作品がより面白くなります。授業で培われた考察力は、社会に出ても役立つと思います。
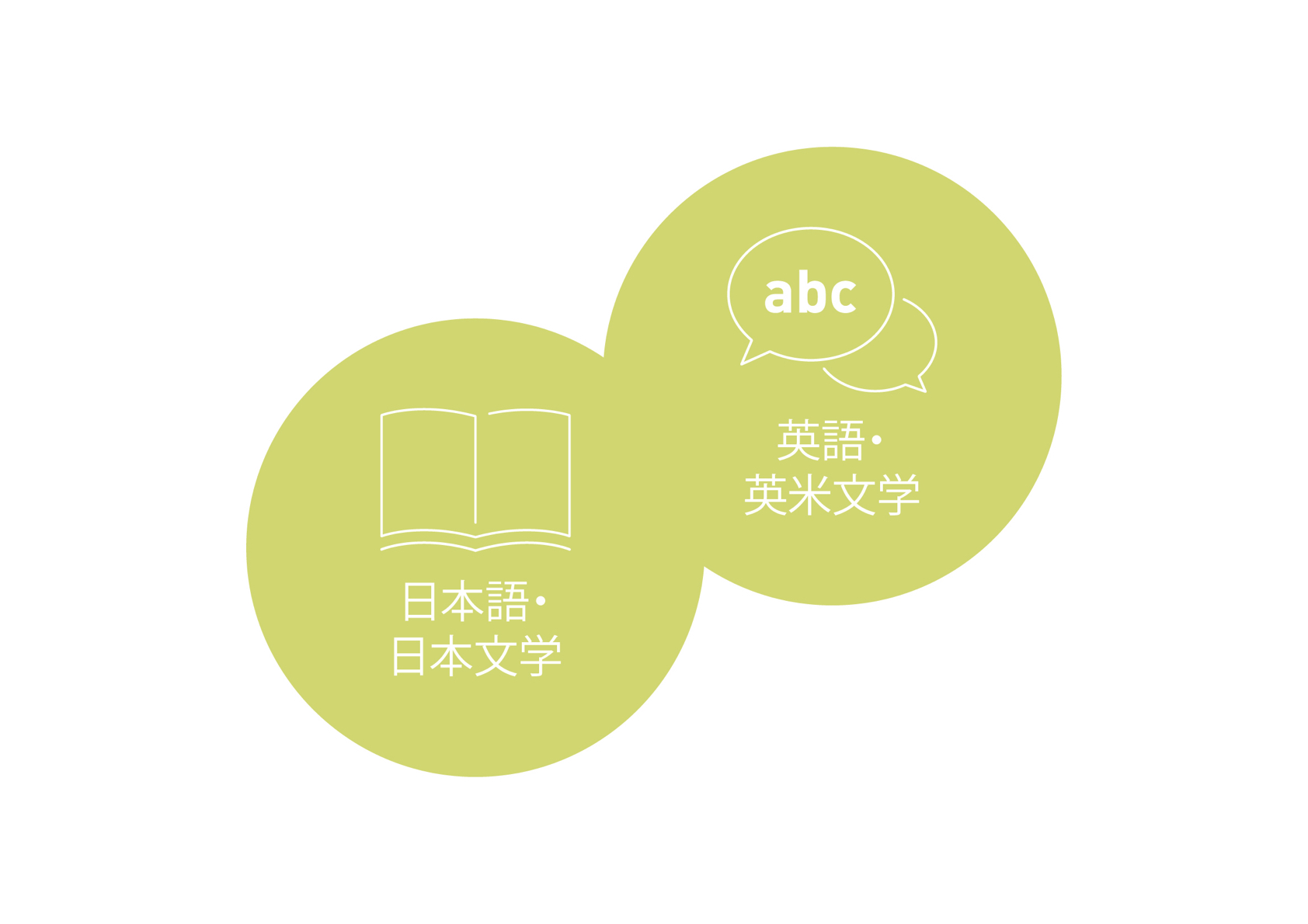
組み合わせて学ぶ
