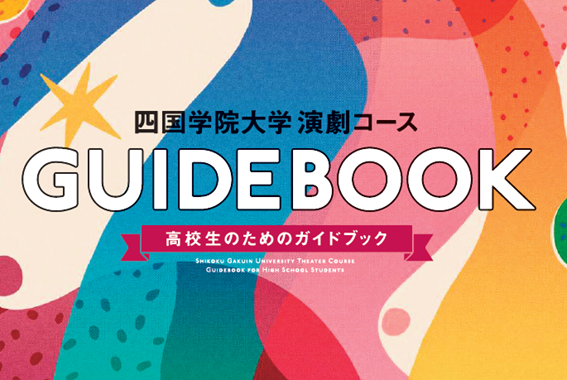演劇ワークショップ実践マイナー

マイナーの学びのポイント
コミュニケーション能力や自主性を磨く
SNSやAIが普及する現代社会では、人との「対話力」が問われています。演劇を使ったワークショップを実践的に学ぶことで、コミュニケーション能力や自主性などのスキルを磨くことができます。
演劇ワークショップをデザインする
演劇やダンスのワークショップは、人と人とをつなぐ役割をします。そんなワークショップを進行することや、地域や、その場所の活性化などを目的としたワークショップをデザインする力を身につけます。
教育や福祉の現場で活かせる学びを得る
教員や福祉関連の仕事を目指す学生にとって、演劇ワークショップを学ぶことは自身の強みになります。学校では学習発表会で活用できたり、福祉の現場ではレクリエーションに活かせたりします。
PICKUP授業
『ワークショップ・デザイン』
様々な分野でのワークショップデザインについて学びます。デザインしたワークショップを現場で実践し、ワークショップファシリテーターとしての役割や、実践的な学びを修得します。
『教育の中の舞台公演実習』
学校教育での演劇・ダンスなどの身体表現活動の役割を考察し、学習発表会・コミュニケーション教育などの校内活動に参画し、ドラマティーチャーとしての学びを深めます。
『社会福祉と演劇ワークショップI』
「当事者研究」を体験し、演劇と社会福祉の関わりについて学びます。また、社会福祉施設等における演劇ワークショップについて考察し、その効果・方法について体系的、実践的に学びます。
学生の声

演劇の力で地元を盛り上げたい。
「社会福祉と演劇ワークショップI」の授業で社会福祉を題材にした公演に参加し、演劇が持つ無限の可能性を実感しました。将来の夢は「地域振興」。働きながらいろいろな企画を立ち上げ、演劇を通じて地元を盛り上げていきたいです。

組み合わせて学ぶ