子ども福祉メジャー

メジャーの学びのポイント
様々な発達課題に応じた支援方法を理解する
子ども(18歳未満)の成長や発達の方法論に触れ、子ども達が成長過程で遭遇する問題や課題を理解します。それぞれの課題に応じた支援方法に接しながら、子ども理解に向けた専門性を養います。
子どもの成長に携わる専門者としての成長を目指す
目の前の人のために努力をすることができることは、子ども福祉の専門性を支える重要な資質です。利他的に他者と向き合う様々な体験活動を通じて、子ども福祉に関わる人としての成長を目指します。
子ども福祉の支援者としての課題を学ぶ
子どもだけでは解決が難しく、解決に向けた支援が必要な家庭を取り巻く問題、人間関係、生活問題に触れることで、子ども福祉の支援者として果たす役割や課題について学びます。
PICKUP授業
『児童・家庭福祉』
児童・家庭の生活実態・社会情勢・福祉環境について概説し、児童の権利、その擁護について考察します。さらに、相談援助活動において必要な児童・家庭福祉制度等について理解します。
『子育ち子育て課題演習I』
子育て家庭の支援や子どもの育ちに携わる支援者が、取り組むべき支援課題のうち、子育て家庭や保護者を取り巻く課題に焦点をあて、子育て家庭に対する支援の必要性と支援課題を考察します。
『マタニティ福祉支援論』
マタニティライフ・ワークライフバランス・産業保健といった、病気も含めた女性全般に関わる知識を理解・修得し、あらゆる角度から女性全般に関わる問題を検討・考察します。
学生の声

分野を超えて保育の可能性を広げていきたい。
保育士を目指しつつ、中学から始めた演劇を続けるために「身体表現と舞台芸術」メジャーも選択。柔軟な制度で社会福祉と演劇の両方を学ぶことができ、いい相乗効果に。保育は実践の場が多数。この経験を地域貢献に生かしたいです。
.jpg)
組み合わせて学ぶ

子どもたちの心のよりどころになりたい。
子どもと関わる仕事に興味があり、保育士の資格取得を目指しています。子どもを取り巻く環境なども知るためにスクールソーシャルワークも同時に学び、視野を広げることができました。将来はみんなに信頼される保育士になりたいですね。
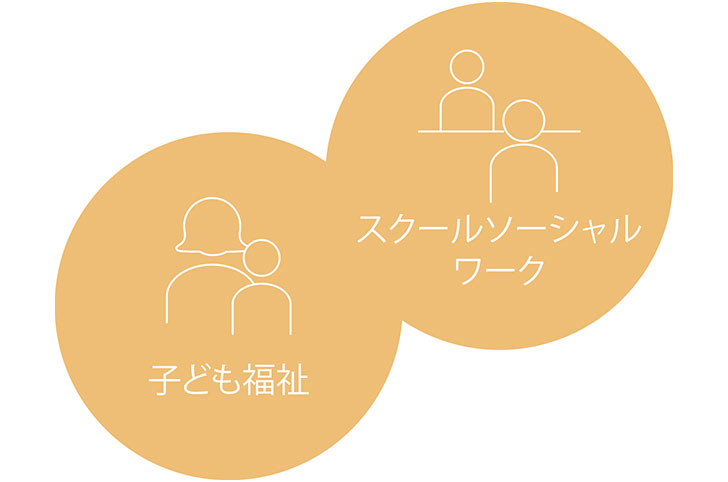
組み合わせて学ぶ
