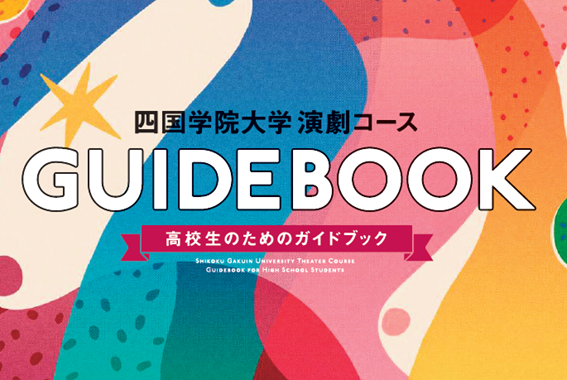アーツ・マネジメント マイナー

マイナーの学びのポイント
アーツ・マネジメントの役割を知る
アーツ・マネジメントとは文化と社会をつなぐための方法論です。アーツ・マネジメントの業務として挙げられる、公演の企画や運営、広報、資金調達などについて具体的に学びます。
表現者と鑑賞者をつなぐ仲介者となる
アーツ活動の遂行に必要な、表現者と鑑賞者を繋ぐ仲介者になるためには、鑑賞の仕方について知ることが重要です。演劇、音楽、映画、美術の分野を中心にアーツ鑑賞について体験的に学び、理解を深めます。
現場実習で実践力を身につける
文化関連法規や国内外の最新の文化芸術政策などの専門的知識を得たあとは、実際に地元の公共ホールや地域の演劇祭などにインターンとして参加し、卒業後即戦力となるような力を身につけます。
PICKUP授業
『アーツ鑑賞入門』
演劇、音楽、映画、美術などの分野を中心に、それぞれのア-ツ分野の基礎事項を修得します。また、ア-ツ鑑賞のために必要な入門的事項について理解を深めます。
『演劇の世界』
主に英米の現代演劇を概観し、代表的戯曲作品をテキストにしながら、演劇の世界の魅力について学びます。演劇の歴史、作品の理解を通して、英米演劇の入門的事項について学びます。
『舞台芸術実習I』
国内外の舞台芸術公演に、観客、俳優、運営スタッフ、ボランティアなどの役割で参加し、現場実習を通して舞台芸術とは何かについての考察を深め、舞台芸術公演の実践力を修得します。
学生の声

大学で知った「アーツ・マネジメント」。芸術で暮らしを豊かに。
専攻にこだわらず、興味のある分野を全て学べるのがこの大学の魅力。アーツ・マネジメントも大学で知り、芸術の意義や関わり方などに興味をそそられました。恵まれた環境でより多くのことを学び、芸術を通して暮らしを豊かにしていきたいです。
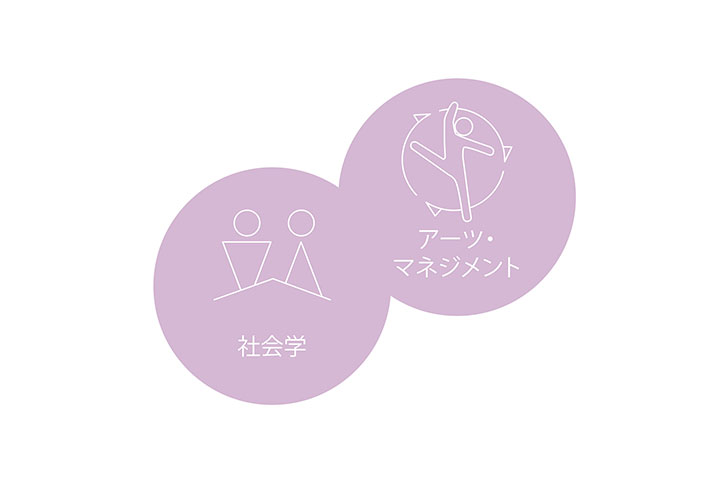
組み合わせて学ぶ