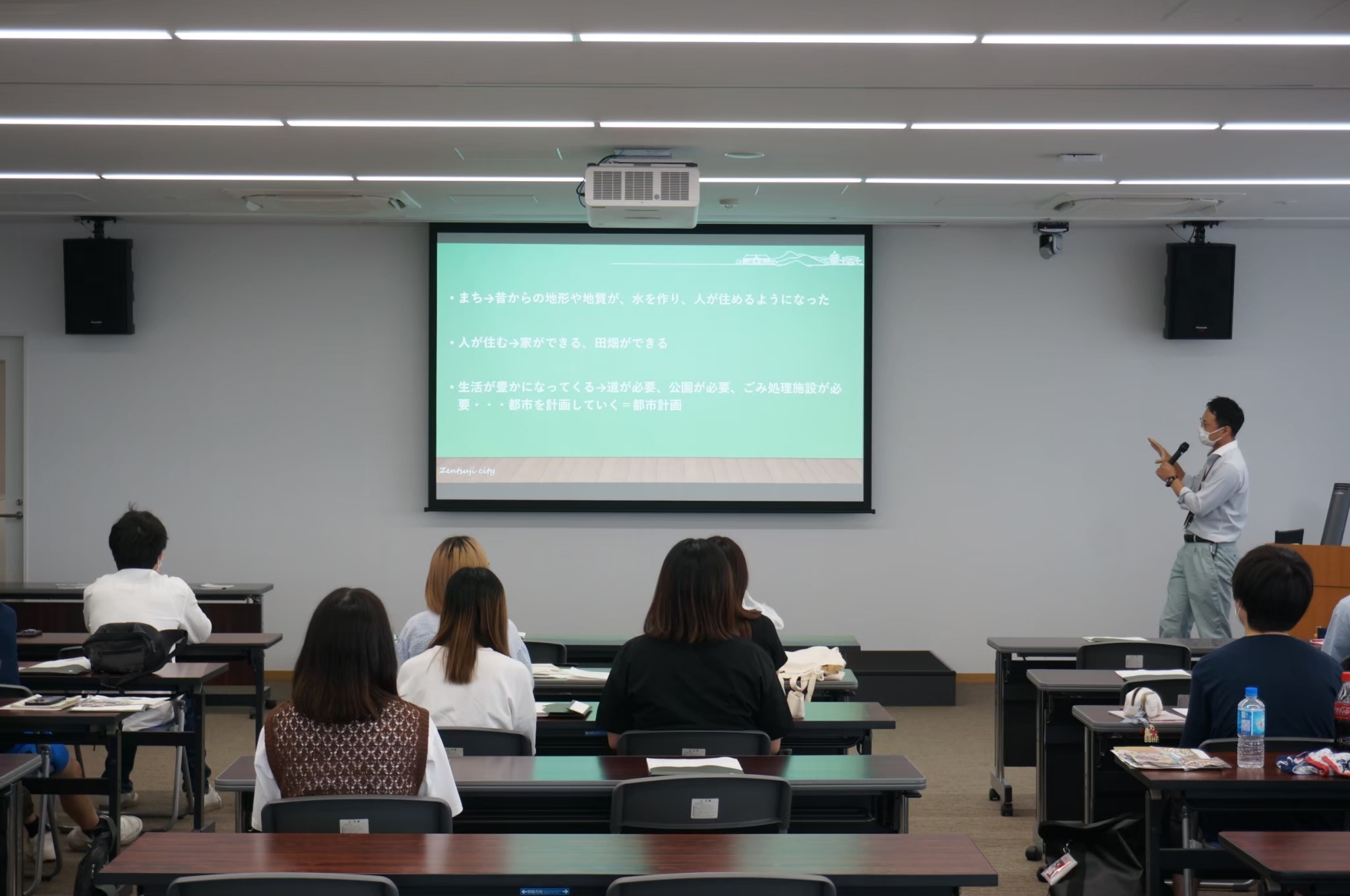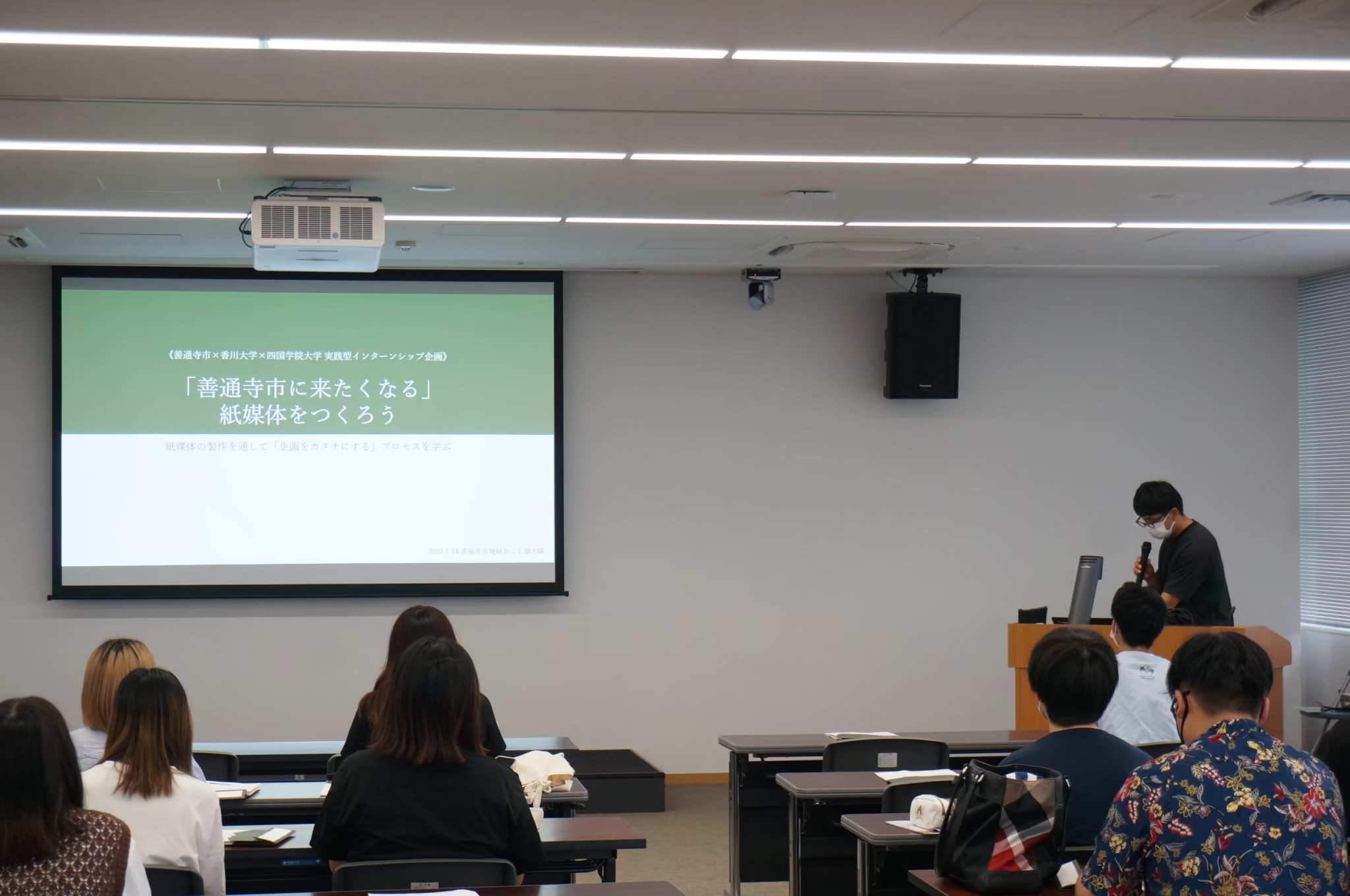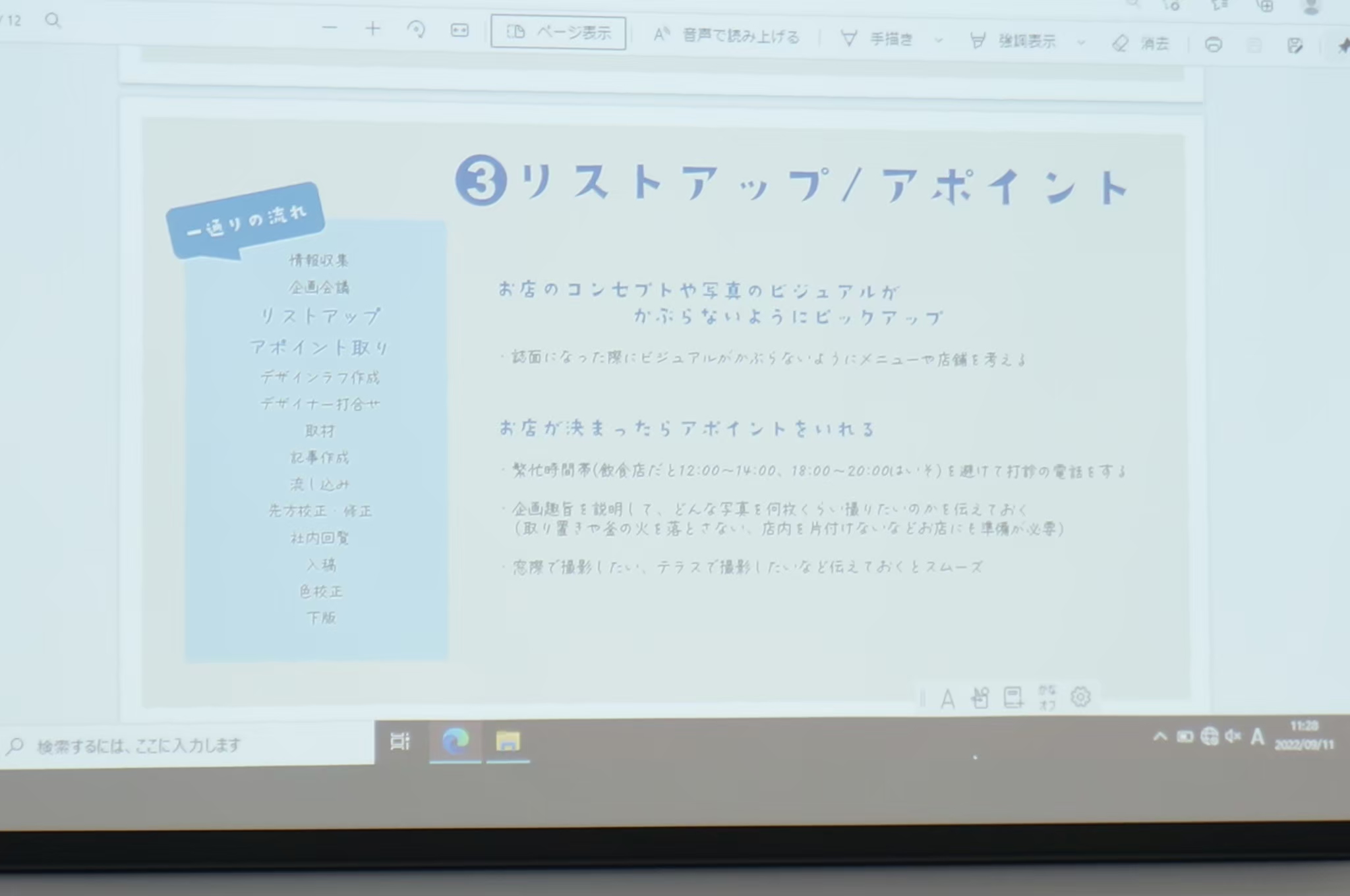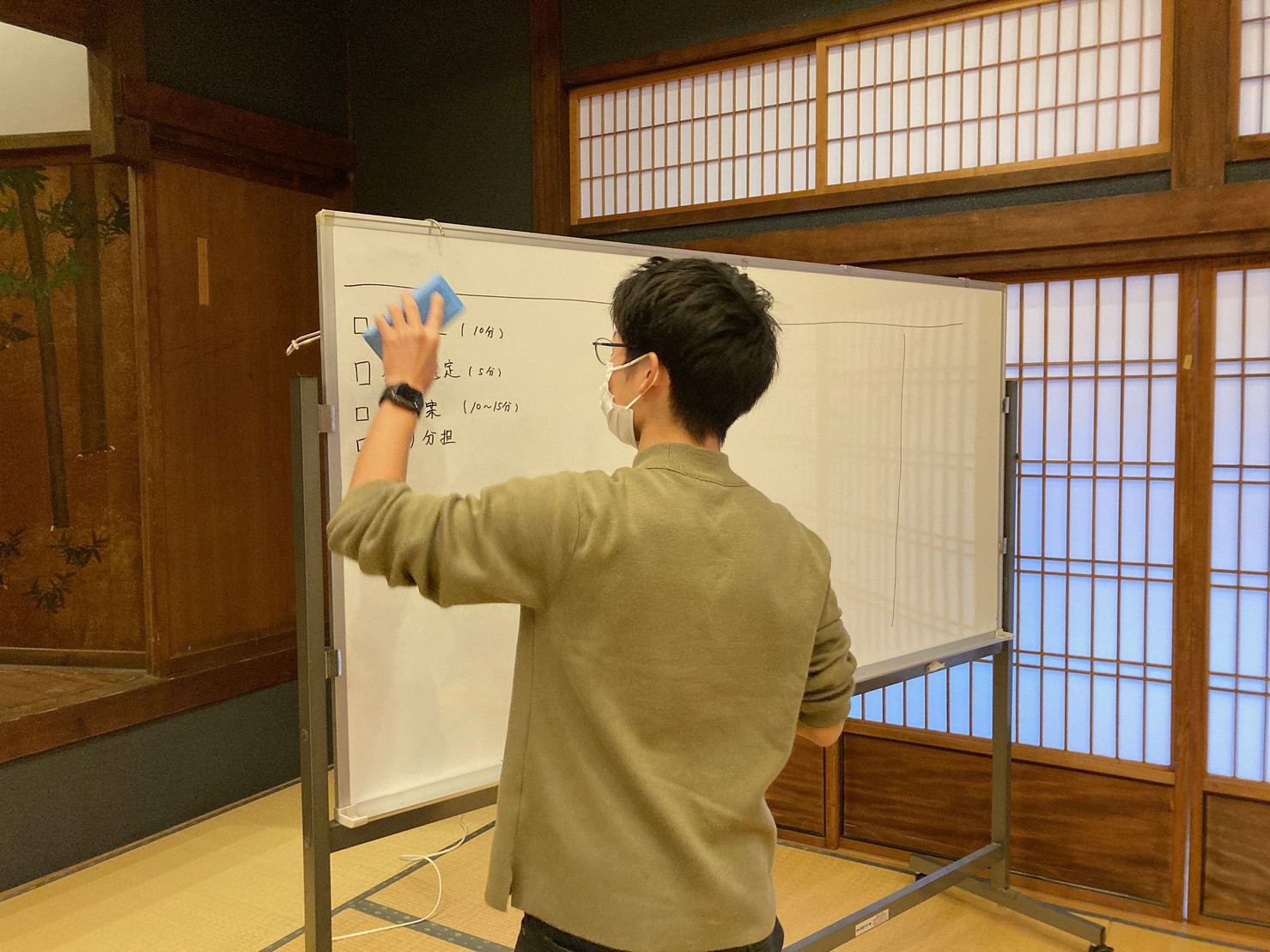社会学部 国際文化マネジメントメジャー 大源心乃さん
倉敷翠松高等学校出身。
韓国の姉妹校 韓南大学校を訪問・滞在して体験する「外国事情(韓国)」。
元々東アジアの歴史に興味があり、授業でも韓国の歴史を学んでいた大源さんは、今回の短期留学で多くの学びを得ることができたそうです。
韓国では、どのような体験をしたのでしょうか?
「外国事情(韓国)」を履修しようと思ったきっかけを教えてください。
――橋本先生の「コリア文化研究」で、韓国の歴史をひと通り学んでいました。授業で使用していた教科書は、韓国人と日本人の先生が一緒に作ったもので、日本人が学校で習う歴史とはちょっと違っていました。歴史っていろんな角度から見たら、また違った解釈になるということを学ぶことができたので、今回「外国事情(韓国)」で実際に自分の目で韓国を見てみたいと思い、参加しました。
「外国事情(韓国)」では、どのような体験をしましたか。
――韓南大学校の学生と一緒に豊臣秀吉が焼き討ちした建物などの歴史的建造物を見て回ったり、世宗という韓国の王様の名前がついている植物園に行ったりしました。ただ、日本人が焼き討ちした建造物や植民地時代のことを思うと、気まずさを感じる場所もありました。実際の歴史がどうだったかは分かりませんが、韓国から見れば、日本は侵略してきた国で、今でも恨みが残っているのも分かるなと思いました。ソウルの景福宮に行った時、植民地時代に建っていた日本総督府は取り払い、地方の土の中に埋められているということを聞きました。同行していた橋本先生は、実際の建物を見たことがあり、「近代的な大きな建物だった」と当時のことを話してくれました。気まずさはありましたが、日本と韓国それぞれの視点を持つ人が一緒に同じ歴史的建造物を見る機会はなかなかないので貴重な体験ができました。
日本の教科書で学ぶのは、第二次世界大戦後にGHQが日本を占領したとか、日本がどれだけ酷いをされたのかということばかりで、日本がアジア諸国にどんなことをしたのかはあまり習うことがありません。でも、韓国の学生は、日本が韓国にしたことを歴史で学んできていると思うので、最近になってその歴史を学んだ日本の学生とで、捉え方は違うんだろうなと感じました。お互いに多くは語りませんでしたが、知らなかった歴史を大学で詳しく学んで、韓国人の学生と実際に歴史的な場所に来ることができたことはよかったと思います。それに、「コリア文化研究」の授業で韓国の歴史を学んでいたからこそ頭に入ってくることも多くて、すごく勉強になりました。

セミナーではどのような発表をしましたか。
――私たちは、「日本のアニメが韓国ではどう変わるのか?」ということをテーマに発表しました。例えば、『銀魂』では沖田総悟というキャラクターが年上や上司のキャラクターにため口で話すシーンなどはすべて敬語になっていたり、『ONE PIECE』のサンジというキャラクターがタバコを吸うシーンはタバコではなくペロペロキャンディーに変わっていたりします。また、仲良くなった韓南大学校の友人の家庭では、日本でよく話題に上がる『クレヨンしんちゃん』ではなく、『ドラえもん』が禁止されていたということを聞いて驚きました。理由を聞いてみると、のび太のようななまけ癖がついたら困るからだと言っていて、そういう見方もあるんだと感じて印象に残っています。セミナーの時に話題になったんですけど、日本は妖怪や鬼をアニメにすることが多くて、韓国は現代を舞台にした作品が多いという違いもありました。日本の伝説や伝承がアニメになっていたりするので、韓国人から見れば新鮮に思えるのかもしれないと感じました。
今回調べたことによって、その国の文化によって、表現の場でも変化や違いがあるということが学べました。
韓国での生活はどうでしたか。
――韓国では寮生活でした。最初は韓国語の勉強もしていなかったし、慣れなかったんですけど、なんとなく一緒にいるうちに「こういうことを言っているのかな?」と分かるようになってきました。翻訳アプリを使って会話をしたり、日本語と英語と韓国語を交えて伝えたり、身振り手振りを使ったりしてコミュニケーションをとるようにしました。一緒にカフェに行ったり、ショッピングをしたり、普段観ているアニメやドラマ、音楽の話で盛り上がったりして、どんどん仲良くなっていきました。
韓国料理がとても美味しかったです。特に印象に残っているのは、カニの素揚げにキムチであえたケジャンという料理です。触感はカリっとしていてピリ辛で、日本にはない料理ということもあって、たくさん食べました。
「外国事情(韓国)」を通して、成長できたことを教えてください。
――韓国人の女子学生と接していて思ったことがあります。それは、そこまで人に気を遣わなくていいのかもしれないということです。私はけっこう人に気を遣ってしまうタイプだったんですけど、韓国の友達は興味がない話題だと「あ、そう」とスパッと会話を切っていて、無理して会話を広げたりしなくてもいいんだと思えました。韓国人の学生との交流で、自分の考え方が変わりました。人間関係で気を遣うことは必要だけど、仲のいい友達との間ではフラットな姿勢で、そこまで気を遣わなくてもいいんだと思うと、気持ちが楽になりました。だから、違う国の文化だし、その子の性格もあるとは思うんですけど、人に気を遣いすぎなくていいということを知ることができて、以前の自分よりは強くなれたと思います。自分が変わることもできたので、本当に韓国に行けてよかったと思います。
また、分からない人に合わせるということも学びました。寮では、韓国人の学生一人と私たち日本人二人が同じ部屋でした。私たちが日本語で話している時、韓国人の学生は何を話しているのか分からない状況になってしまいます。私はその子と仲良くなりたかったし、疎外感を感じてほしくなかったので、日本語での会話が終わったら、翻訳アプリを使ってどういう話をしていたのか、ということを伝えるようにしていました。そういったコミュニケーションをとっていたおかげで、些細なことでもお互いに翻訳アプリを使って会話するようになって、より仲良くなることができました。これは言語だけの話ではなくて、同じ空間で分かる人と分からない人がいる時には、分からない人に合わせてコミュニケーションをとっていくことがその人と仲良くなる上で大切なんだと学びました。

四国学院大学に入学した理由を教えてください。
――オープンキャンパスで受けた金先生の授業が面白くて、金先生の授業をもっと受けてみたいと思ったからです。それに、友人の付き添いで個別相談に行った時、同じ岡山出身の職員の方がいて話が盛り上がったこともあって、この大学で過ごすのはすごく楽しそうだなと感じて入学を決めました。
国際文化マネジメントメジャーでの学びはどうですか?
――いろんな国の歴史を知りたかったので、メジャー選択の時には歴史学・地理学メジャーと迷ったんですけど、いろんな国の事情をいろんな角度から見たかったので国際文化マネジメントメジャーに決めました。国際文化でイギリス史や韓国史などを学べているし、メジャー制度のおかげで他の分野の授業も履修できるので、オープンキャンパスで気になっていた金先生の授業も受けたりしながら、すごく楽しく学んでいます。
特に学んだことで印象に残っているのは、韓国史です。隣の国の歴史なのに、義務教育では深く学ぶことがありません。だから、意外と接点があったんだということも知ったし、日本が韓国に対して何をしたのかも知ることができたし、日本での出来事が韓国ではどうだったのか、と比較しながら学ぶことができました。例えば、日本が終戦を迎えた時に韓国は植民地時代が終わったから光を取り戻したとか。日本にもきっと朝鮮系の人もいて、同じ祖先を持つ人もいるのに、その国の文化によって考え方や見方が変わってくるというのがすごく面白かったです。
そういったことを学んだ上で「外国事情(韓国)」で実際に韓国に行くことができたので、メジャーでの学びの一環のようですごく勉強になりました。
これからの将来にどう活かしていきたいか。
――分からない人に合わせる、というのが自分にすごく勉強になったことでした。これから国際文化に係る仕事に就くかは分からないんですけど、人に気を遣いすぎなくてもいいとか、分からない人に合わせるとか、お互い分かろうと努力していけばけっこう仲良くなれるということを知れたので、これから人間関係を築いていく上で大切なことを学ぶことができたと思います。
「外国事情(韓国)」に興味がある人へアドバイスやメッセージがあればお願いします。
――韓国に興味を持っている人が多く選ぶと思うんですけど、外国の人と関わってみたいとか、外国ってどうなんだろうとフワッとした興味がある人でも勉強になると思います。視野を広げるために行くのもアリだと思います。後からでも自分に吸収できることがあると思うので、とりあえず行くことが大事です。それに、韓国の学生とずっと一緒に過ごすのは、学生の今しかできないと思います。そういう目標や目的があってもなくても、行ってみたら勉強になることがたくさんあるはずです。
「外国事情(韓国)」とは…
サマ-セッションの一週間、韓国大田市にある姉妹校韓南大学校を訪問・滞在し、韓日国際学生セミナ-に参加して韓国の大学生と友好親善交流をし、韓国各地を訪ね人々と直接的な出会いを体験しながら、韓国の歴史や文化、韓国人の日常生活などについての理解を深める韓国体験授業です。